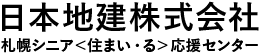ブログ
「身元保証契約」や「財産管理・事務委任契約」「任意後見契約」について
~行政書士ほそだ宮の森事務所 細田 健一先生に聞きました~
札幌シニア<住まい・る>応援センターでは、おひとり暮らしの高齢者の方より「ご自宅での生活が加齢により難しくなってきたため、ご自宅を売却して有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅に入居したい」とのご相談がよくあります。
今回は、そういった住宅事業者にスムーズに入居を受け入れてもらうための制度について、昨年6月に公表された「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」との関係も含めて,細田先生にお伺いしました。
1.身元保証契約(サービス) (※注)
目的は,身寄りがいない,若しくは頼れるご家族がいない高齢者の方に対し施設・病院との間で身元保証人に就任して,施設や病院に入居・入院してもらうものです。
高齢者施設への入居や病院への入院の際などに必要となるのが「身元保証人」です。いざ,施設に入居したいとなっても,近くに頼れるご家族がいない場合や身寄りがない方にとって大きなハードルになります。このような事態に対応するために,入院時や施設入居時の身元保証人となるものです。保証料と対応料が発生します。
2.財産管理・事務委任契約(サービス) (※注)
目的は,財産管理に不安な依頼者に対して通帳等を預かり依頼者の財産を適切に管理するものです。
依頼者が元気なときに,財産管理の範囲・方針等を事前に契約で定めておきます。受任者は契約に基づいて財産を管理しその事務を執り行います。判断能力自体に問題のない段階までは,継続していくことができます。
しかし,本人の判断能力が低下した場合,本人の第三者に対するチェック機能が不十分になるリスクがあります。
そこで,後述する「移行型の任意後見契約」を同時に締結しておきます。「移行型」とは,財産管理契約を締結して,受任者が財産管理を行い,本人の判断能力が低下した後に任意後見契約を発効させて任意後見人が財産管理を行うとするものです。
3.任意後見契約
成年後見制度の種類には,「法定後見制度」と「任意後見契約」の2つあります。
〇「法定後見制度」は、認知症等が発症又は悪化して判断能力が不十分になった場合に、
家族の申立てにより,家庭裁判所が,その者を保護する者を選任する制度です。
〇「任意後見契約」とは,本人が,判断能力に問題がない段階において,委任者として,精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における本人の生活,療養看護及び財産管理を行う第三者=「任意後見人」を選び,事務について代理権を付与する委任契約です。
実際に判断能力が不十分になったときに,家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て,裁判所から選任されたときに,任意後見契約の効力が発効します。
任意後見監督人選任の申立ては,本人の同意を得て受任者である任意後見人が行う場合が多いと思われます。
<任意後見契約の特徴について,法定後見制度と比較しながら,以下にみていきましょう>
① 法定後見制度の場合は,最終的に後見人等を選任するのは裁判所であり,必ずしも本人の希望通りの者が後見人等に選任されるとは限りません。
② 任意後後見制度では、法定後見制度と異なって,法律行為に対する取消権が認められていません。また,代理権は認められていますが,その範囲は各類型事案ごとに委任者との合意で決められます。
③ 任意後見契約は,必ず「公正証書」によってなされなければなりません。公証人が関与することにより,本人の真意に基づいた適正な契約が締結されることが期待されています。
④ 任意後見契約は,実際に判断能力が不十分になったときに,家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て,裁判所から選任されたときに,任意後見契約の効力が発効します。家庭裁判所は,本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ任意後見監督人の選任の審判をすることができません。
<任意後見契約の3つの形態>
任意後見契約には,将来型,移行型,即効型の3つの形態があるとされています。
(1)将来型
将来型は,契約締結時には任意後見受任者において何らかの事務が発生することはなく,将来本人の判断能力が低下した時点で,任意後見受任者が任意後見監督人の監督の下に任意後見契約に基づき事務を開始する形態です。
契約締結の後,実際に任意後見人の財産管理が開始するまでの間にかなりのタイムラグが存在することがあり,その間,本人と任意後見人との間の信頼関係をいかに維持するかが問題となります。
(2)移行型★お奨め
移行型は,財産管理契約を締結して,任意後見契約発効前から受任者が見守りや財産管理を行い,本人の判断能力が低下した後に任意後見契約を発効させて任意後見人が財産管理を行うとするものです。
移行型は,将来型の問題として指摘した委任者と受任者の信頼関係の維持の間隙を埋めるものとして有効なものとされています。
(3)即効型
即効型は,任意後見契約の締結後,直ちに任意後見契約を発効させるものです。この段階では,本人の判断能力が一定程度低下していることから,本人に同契約を締結する能力が備わっているか,本人が同契約の内容をきちんと理解できているか,ということが常に問題となり得,後日,同契約の有効性が争われる可能性があり得ます。
<医療行為,死後事務,報酬について>
本人が受任者(任意後見人)に代理権を付与できるのは,自己の生活,療養看護及び財産管理に関する法律行為に関するものに限られます。
医療行為,特に終末期医療に関する意向や本人が死亡した後の葬儀や供養に関する事項については任意後見契約で定めることはできません。
任意後見契約とは別に尊厳死宣言公正証書を作成したり,死後事務委任契約(※注)を締結しておくなどの対応を検討します。
ところで,任意後見監督人には報酬請求権が認められており,任意後見人にも報酬を認めている場合には,2人に報酬を支払うことになるので,見過ごすことのないよう注意しましょう。
(※注)解説:「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に係る業務について
・令和6年6月,内閣官房及び関係の8府省庁から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(以下,ガイドライン。)が公表されました。
・本ガイドラインは,事業者の適正な事業運営を確保し,健全な発展を推進し,利用者が安心してサービスを利用できることに資するようにするために策定されました。
・「高齢者等終身サポート事業」とは,主に高齢者を対象とする「身元保証サービス」,「死後事務サービス」,「日常生活支援サービス」に分類されるサービスで,近年,急速に事業者数が増加し,それとともに消費者からの相談や消費者トラブルも増加していることから,本ガイドラインの策定に至りました。
・本ガイドラインでは,事業者に対し,契約締結にあたり,契約内容の適切な説明を求める他,医療・介護関係者等との連携や,推定相続人への説明を推奨しています。
・契約の履行に当たっては,提供したサービスの時期や内容,費用等の記録を作成,保存,定期的な利用者への報告の重要性を指摘するとともに,寄附・遺贈を契約条件にすることは避けるとか,前払金(預託金)の事業資金と明確に区分管理することを求めているほか,透明性の確保と消費者の利益保護を強調しています。
・ただし,本ガイドラインは,各種業法による規制が及ばない事業者について一定の指針を示すものであって,弁護士,司法書士,行政書士等の業法に基づく規制等が既に存在している業種は対象外になっておりますので,ご注意下さい。
<補足:弊社のスタンスについて>
弊社としましては,「終身サポート事業」に限らず,これまでもお客様からのご相談につきましては,連携先の士業を中心にご紹介してまいりましたところ, 本ガイドラインを踏まえ,士業に加えて,外部事業者との連携が必要なときはガイドラインを遵守する事業者を確保するよう努め,利用者様の利益保護に取り組んでまいります。
<この記事を書いた人>
行政書士ほそだ宮の森事務所

代表行政書士 細田 健一(ほそだ けんいち)
札幌市中央区の「行政書士ほそだ宮の森事務所」は,「終活」「相続」「身元保証」「認知症対策」「死後事務手続き」を専門としています。地域の介護,医療,福祉,行政,葬祭各関係者と連携し相談者の課題を総合的に解決することを目指しています。1年で約30回のセミナー・講座に登壇し,札幌市介護予防事業「すこやか倶楽部」の終活講座の講師として分かりやすい解説が人気です。
******************************************
北海道札幌市中央区宮の森2条17丁目7番7号
電話番号 090-9529-1272
営業時間 平日午前9時~午後5時
安心の初回無料相談。自宅にいながら相談(出張対応・リモート相談対応)。見積もり提示!
札幌シニア<住まい・る>応援センターでは、おひとり暮らしの高齢者の方より「ご自宅での生活が加齢により難しくなってきたため、ご自宅を売却して有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅に入居したい」とのご相談がよくあります。
今回は、そういった住宅事業者にスムーズに入居を受け入れてもらうための制度について、昨年6月に公表された「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」との関係も含めて,細田先生にお伺いしました。
1.身元保証契約(サービス) (※注)
目的は,身寄りがいない,若しくは頼れるご家族がいない高齢者の方に対し施設・病院との間で身元保証人に就任して,施設や病院に入居・入院してもらうものです。
高齢者施設への入居や病院への入院の際などに必要となるのが「身元保証人」です。いざ,施設に入居したいとなっても,近くに頼れるご家族がいない場合や身寄りがない方にとって大きなハードルになります。このような事態に対応するために,入院時や施設入居時の身元保証人となるものです。保証料と対応料が発生します。
2.財産管理・事務委任契約(サービス) (※注)
目的は,財産管理に不安な依頼者に対して通帳等を預かり依頼者の財産を適切に管理するものです。
依頼者が元気なときに,財産管理の範囲・方針等を事前に契約で定めておきます。受任者は契約に基づいて財産を管理しその事務を執り行います。判断能力自体に問題のない段階までは,継続していくことができます。
しかし,本人の判断能力が低下した場合,本人の第三者に対するチェック機能が不十分になるリスクがあります。
そこで,後述する「移行型の任意後見契約」を同時に締結しておきます。「移行型」とは,財産管理契約を締結して,受任者が財産管理を行い,本人の判断能力が低下した後に任意後見契約を発効させて任意後見人が財産管理を行うとするものです。
3.任意後見契約
成年後見制度の種類には,「法定後見制度」と「任意後見契約」の2つあります。
〇「法定後見制度」は、認知症等が発症又は悪化して判断能力が不十分になった場合に、
家族の申立てにより,家庭裁判所が,その者を保護する者を選任する制度です。
〇「任意後見契約」とは,本人が,判断能力に問題がない段階において,委任者として,精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における本人の生活,療養看護及び財産管理を行う第三者=「任意後見人」を選び,事務について代理権を付与する委任契約です。
実際に判断能力が不十分になったときに,家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て,裁判所から選任されたときに,任意後見契約の効力が発効します。
任意後見監督人選任の申立ては,本人の同意を得て受任者である任意後見人が行う場合が多いと思われます。
<任意後見契約の特徴について,法定後見制度と比較しながら,以下にみていきましょう>
① 法定後見制度の場合は,最終的に後見人等を選任するのは裁判所であり,必ずしも本人の希望通りの者が後見人等に選任されるとは限りません。
② 任意後後見制度では、法定後見制度と異なって,法律行為に対する取消権が認められていません。また,代理権は認められていますが,その範囲は各類型事案ごとに委任者との合意で決められます。
③ 任意後見契約は,必ず「公正証書」によってなされなければなりません。公証人が関与することにより,本人の真意に基づいた適正な契約が締結されることが期待されています。
④ 任意後見契約は,実際に判断能力が不十分になったときに,家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て,裁判所から選任されたときに,任意後見契約の効力が発効します。家庭裁判所は,本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ任意後見監督人の選任の審判をすることができません。
<任意後見契約の3つの形態>
任意後見契約には,将来型,移行型,即効型の3つの形態があるとされています。
(1)将来型
将来型は,契約締結時には任意後見受任者において何らかの事務が発生することはなく,将来本人の判断能力が低下した時点で,任意後見受任者が任意後見監督人の監督の下に任意後見契約に基づき事務を開始する形態です。
契約締結の後,実際に任意後見人の財産管理が開始するまでの間にかなりのタイムラグが存在することがあり,その間,本人と任意後見人との間の信頼関係をいかに維持するかが問題となります。
(2)移行型★お奨め
移行型は,財産管理契約を締結して,任意後見契約発効前から受任者が見守りや財産管理を行い,本人の判断能力が低下した後に任意後見契約を発効させて任意後見人が財産管理を行うとするものです。
移行型は,将来型の問題として指摘した委任者と受任者の信頼関係の維持の間隙を埋めるものとして有効なものとされています。
(3)即効型
即効型は,任意後見契約の締結後,直ちに任意後見契約を発効させるものです。この段階では,本人の判断能力が一定程度低下していることから,本人に同契約を締結する能力が備わっているか,本人が同契約の内容をきちんと理解できているか,ということが常に問題となり得,後日,同契約の有効性が争われる可能性があり得ます。
<医療行為,死後事務,報酬について>
本人が受任者(任意後見人)に代理権を付与できるのは,自己の生活,療養看護及び財産管理に関する法律行為に関するものに限られます。
医療行為,特に終末期医療に関する意向や本人が死亡した後の葬儀や供養に関する事項については任意後見契約で定めることはできません。
任意後見契約とは別に尊厳死宣言公正証書を作成したり,死後事務委任契約(※注)を締結しておくなどの対応を検討します。
ところで,任意後見監督人には報酬請求権が認められており,任意後見人にも報酬を認めている場合には,2人に報酬を支払うことになるので,見過ごすことのないよう注意しましょう。
(※注)解説:「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に係る業務について
・令和6年6月,内閣官房及び関係の8府省庁から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(以下,ガイドライン。)が公表されました。
・本ガイドラインは,事業者の適正な事業運営を確保し,健全な発展を推進し,利用者が安心してサービスを利用できることに資するようにするために策定されました。
・「高齢者等終身サポート事業」とは,主に高齢者を対象とする「身元保証サービス」,「死後事務サービス」,「日常生活支援サービス」に分類されるサービスで,近年,急速に事業者数が増加し,それとともに消費者からの相談や消費者トラブルも増加していることから,本ガイドラインの策定に至りました。
・本ガイドラインでは,事業者に対し,契約締結にあたり,契約内容の適切な説明を求める他,医療・介護関係者等との連携や,推定相続人への説明を推奨しています。
・契約の履行に当たっては,提供したサービスの時期や内容,費用等の記録を作成,保存,定期的な利用者への報告の重要性を指摘するとともに,寄附・遺贈を契約条件にすることは避けるとか,前払金(預託金)の事業資金と明確に区分管理することを求めているほか,透明性の確保と消費者の利益保護を強調しています。
・ただし,本ガイドラインは,各種業法による規制が及ばない事業者について一定の指針を示すものであって,弁護士,司法書士,行政書士等の業法に基づく規制等が既に存在している業種は対象外になっておりますので,ご注意下さい。
<補足:弊社のスタンスについて>
弊社としましては,「終身サポート事業」に限らず,これまでもお客様からのご相談につきましては,連携先の士業を中心にご紹介してまいりましたところ, 本ガイドラインを踏まえ,士業に加えて,外部事業者との連携が必要なときはガイドラインを遵守する事業者を確保するよう努め,利用者様の利益保護に取り組んでまいります。
<この記事を書いた人>
行政書士ほそだ宮の森事務所

代表行政書士 細田 健一(ほそだ けんいち)
札幌市中央区の「行政書士ほそだ宮の森事務所」は,「終活」「相続」「身元保証」「認知症対策」「死後事務手続き」を専門としています。地域の介護,医療,福祉,行政,葬祭各関係者と連携し相談者の課題を総合的に解決することを目指しています。1年で約30回のセミナー・講座に登壇し,札幌市介護予防事業「すこやか倶楽部」の終活講座の講師として分かりやすい解説が人気です。
******************************************
北海道札幌市中央区宮の森2条17丁目7番7号
電話番号 090-9529-1272
営業時間 平日午前9時~午後5時
安心の初回無料相談。自宅にいながら相談(出張対応・リモート相談対応)。見積もり提示!
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする